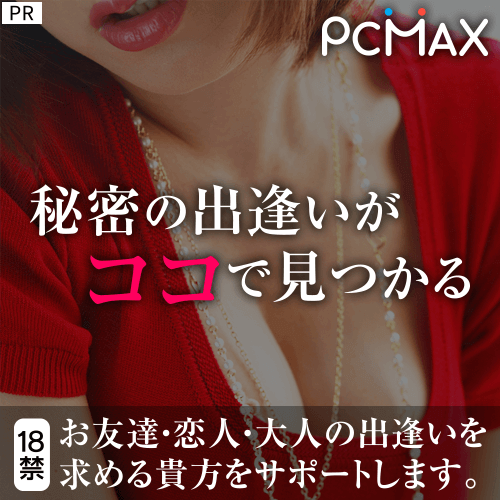「もう“恋”とかどうでもいい。でも、触れ合いが欲しい。」
ある平日の夜、そんな書き出しのプロフィールに目を奪われた。
出会い系アプリ「PCMAX」に登録してからもう3年。最初は興味本位だったが、今では日常の“抜け道”のような存在になっている。
その日もなんとなく掲示板を覗いていたら、「細身で寂しがりなシングルマザーです。都内で会える方希望」という書き込みが目に入った。アイコンには顔の写っていないボディラインが映っていて、かなり華奢な印象。そして「Fカップ」との自己申告。正直、細身でFカップというだけで男性の想像力は勝手に膨らむ。
すぐにメッセージを送った。

最初のやり取り──彼女の“現実”
「こんにちは、プロフィール拝見しました。都内住みで、同じように夜は少し寂しい時があります。」
そんな軽めの挨拶に、彼女からの返信は思った以上に早かった。
「今、息子を寝かしつけてやっと一息です。…寂しいって、男の人でもあるんですね。」
彼女は「真奈美(仮名)」という33歳のシングルマザーだった。離婚して3年、現在はパートで働きながら小学生の息子を育てているという。元旦那との離婚理由は「レス」と「生活のすれ違い」。それでも子どもがいたから我慢していたが、ある日、完全に愛情も欲も枯れ果てたように感じて、別れを選んだそうだ。
「子どもと2人の生活は幸せ。でも、女としての部分がずっと置き去りで…」
そんな言葉に、妙にリアリティがあった。エロさではなく、**“生身の女の欲求”**を感じさせる言葉だった。
会う約束──現実と非現実の境界線
3日後、金曜日の夜。彼女が実家に子どもを預けられる日とのことで、都内のカフェで会うことになった。
待ち合わせ場所に現れた真奈美は、白のロングスカートに黒のカーディガンという控えめな装い。いかにも“普通のママ”という雰囲気だったが、近くで見るとその華奢な体には確かにFカップが主張していて、静かな色気が滲んでいた。
「写真よりずっと綺麗ですね」と伝えると、「よく言われます…ネットって便利だけど、怖いですよね」と照れ笑いを浮かべた。
カフェでは、子どもの話、仕事の愚痴、元旦那のこと…“普通の母親”としての彼女がいた。けれど、その合間にふと漏れる言葉の節々に、「ずっと抱かれてない」という切実な想いが垣間見える。
ホテルへ──“母”から“女”へ
2時間ほど会話した後、自然な流れで近くのホテル街へ向かった。緊張していたのは、むしろ彼女の方だった。
「こういうの、ほんと久しぶりで…なんか、変な感じ…」
部屋に入ってもすぐに身体を重ねることはせず、彼女はシャワーを浴びて戻ってきた。バスタオル1枚を巻いたその姿は、明らかに母親ではなく“女”だった。
その後、自然に抱きしめて唇を重ねた。肌はすべすべで、細身の体は抱き心地がよく、しかもFカップの柔らかさは信じられないくらいリアルだった。
ベッドの上では、最初は恥じらっていた彼女も、時間が経つにつれて次第に大胆になっていった。

彼女の欲望──“我慢”の果てにあったもの
「ずっと我慢してたの、いろんなこと…」
そんな一言をきっかけに、彼女の中に溜め込まれていた“欲望”が溢れ出した。
クンニをしていると、何度も腰を浮かせるように悶え、潮を吹いた。声を抑えきれず、枕に顔を埋めて泣くように喘いでいた。
「こんなの…恥ずかしいくらい気持ちいい…」
その後も、手コキやパイズリ、素股といったプレイを交えながら、終始濃厚な時間を過ごした。セックス自体は久しぶりとのことで、体の反応がとても敏感で、ひとつひとつの触れ合いに対して素直だった。

ベッドの余韻──また“母”へ戻る瞬間
事後、彼女は静かにシャワーを浴びたあと、髪を乾かしながらこう言った。
「やっぱり私、母親じゃなくて“女”でもあったんだなって、思い出せた。」
その言葉はどこか寂しく、でも確かに満たされていたように聞こえた。
別れ際、LINEを交換したものの、彼女からは「次も期待しないでくださいね」と釘を刺された。子どものことが最優先で、こういう時間を取れるのは“奇跡”のようなものだという。
あの夜を振り返って
「シングルマザー」と言えば、どこか遠い存在に感じていた。でも、実際に会ってみると、そこには“普通の女性”がいて、愛に飢え、欲に揺れる一人の人間がいた。
そして彼女は、確かに“抱かれたかった”。恋でも愛でもなく、ただ“求められたかった”のだ。
出会い系は危険だとよく言われる。でも、こんなふうに「本音を晒せる場所」があってもいいと、俺は思う。真奈美のように、母であると同時に“女”でもある存在が、それを思い出せる場として。
そんな夜を過ごしたことは、きっと俺の記憶に長く残る。