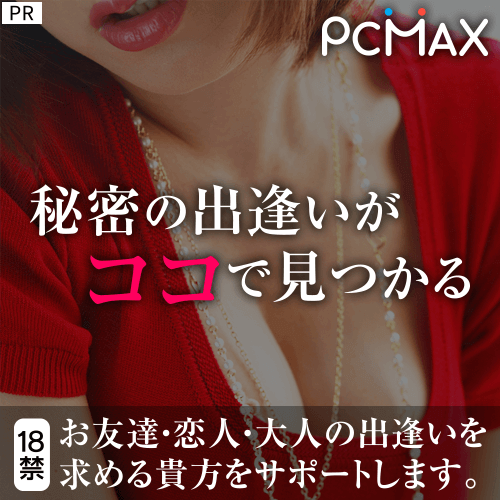-
相手:30代半ばの女性バーテンダー
-
職業:大阪・北新地の会員制バー勤務/元モデル・現役で裏垢女子として活動中
-
属性:長髪・巨尻・Fカップ・美脚/スレンダーかつ肉付きの良い下半身/ドS気質
-
性癖:手コキ・アナル舐め・フェラ・連続中出し・首絞め・ローター・潮吹き・撮影・羞恥・顔射
-
出会い:Jメールの趣味友掲示板で接触→PCMAXに移動→セフレ化
-
プレイ内容:バーカウンターでの手マン/化粧をしたままの激しいプレイ/バイブ装着での接客
-
舞台:大阪府北新地→梅田→立花→姫路(出張プレイ含む)
-
欲望:彼氏では満たされない性欲/遊び目的/セフレ募集/週末限定の肉体関係
-
使用アプリ・掲示板:Jメール・PCMAX・安心・安全なサイト・セフレ掲示板・裏垢女子垢から逆ナンも
「ここ、閉めたら……あたしんとこ、来る?」
彼女はバーのグラスを片付けながら、カウンター越しにそう言った。
その声は低く、酒と煙草にくぐもっていて、どこか男っぽささえ感じる。だが、その指先やヒップラインは完全に“女”だった。
出会いのきっかけは、Jメールの趣味友掲示板。
「週末限定/北新地でバーテンダーしてます/会話と酒と…時々、欲しいもの。」
そんな短い投稿に、なぜか惹かれた。「バー、やってるけど昼間は暇でさ。誰か、暇つぶしてくれる?」
最初の返信は、淡々としていた。
だが、2往復目でLINEを交換し、3往復目で「会ってみる?」と誘われた。その夜、僕は北新地の小さなバーにいた。
彼女の名前は沙月(さつき)。元モデルだという。Fカップの巨乳と張りのある巨尻、腰のくびれ、スレンダーなのに肉感的なバランスに、思わず息をのんだ。
「撮られてもいいよ。顔以外なら。……その代わり、撮り返すけど?」
彼女はカウンターの奥でグラスを拭きながらそう言った。
既にバイブと電マが入った専用ポーチがカウンター下にあるのを、僕は見ていた。彼女の言う「撮り返す」とは、自分のプレイ動画を自分で編集して保存しているということだった。
「裏垢では出してないよ。セフレ限定のやつ。……あんた、そこに入りたい?」
初めてのプレイは、バーの閉店後。
隠し扉の奥、オーナーしか使わないソファスペースに連れて行かれた。「音、漏れないようになってる。そういう用途の店だから」
言いながら、沙月はシャツのボタンを一つずつ外していった。
レースの下着からは、乳首の色が透け、Fカップが揺れるたびにため息が漏れた。「まずは……あたしが癒されたい」
彼女は僕の手を自らの太ももに導き、ローターをTバックの隙間から差し込んでいった。
「強めにして。遠慮すんな」数分後、彼女は僕の膝の上に座り、舌を絡ませながらこう囁いた。
「撮って。手でしてるとこ、撮って。あんたの手で、私、イくから」
それが始まりだった。
翌週、彼女はPCMAXで再登録し、そこから本格的に関係が始まった。
「Jメールは出会い用。PCMAXはセフレ探し専用」と言い切る彼女は、複数の男と連絡を取りながらも「週末はあんた優先」と笑った。
■ 2回目──立花のホテル、潮吹きの夜
「今日は、電マと首絞め、どっち先がいい?」
立花駅近くのホテルで、彼女はベッドに寝転びながら聞いてきた。
僕が戸惑っていると、「両方してくれればいいから」と言って、ローションをたっぷり身体に垂らした。プレイは激しかった。
首を軽く絞めながら、バイブと電マを同時使用し、彼女は4回以上絶頂した。「この部屋、全部濡れたね。……シーツ代、払っといて?」
そう言って、彼女は笑った。
汗と潮と香水の香りが混じった匂いに、僕は完全に酔っていた。
■ 3回目──姫路、ホテルの夜
「今日は出張で姫路。来ない? 経費で部屋取ってるし、空いてるよ」
そんなLINEが来て、僕はその日の最終の新幹線に乗った。
ホテルに着くと、彼女はすでにバイブを挿れた状態で、ベッドで開脚して待っていた。「このまま撮って。音、拾って。……自分で聴き返すの、好きなの」
アナル責め、顔射、撮影、潮吹き、そして最後に中出し。
「避妊してるから、大丈夫。……でも、あんたの、欲しかったの」
その夜、彼女は完全にとろけた顔で何度もイった。
■ 告白と終焉
次に会った夜、沙月はこう言った。
「彼氏、できた。でもセックス、相性悪い。……だから、続けていい?」
もちろんと答えた。
「セフレって、彼氏と違って“本音”でできるから楽じゃん。
こうして、首絞めて、潮吹いて、撮られて……彼には言えないでしょ?」
それから数ヶ月、僕らは月に2〜3回会っていた。
梅田、天王寺、立花、姫路……彼女の出張先に合わせて。「セフレって、誰よりも“わたし”を知ってる存在だと思ってる。
性癖も、弱さも、全部見せてるから──」だがある日、LINEが既読にならなくなった。
数日後、PCMAXの彼女のアカウントも消えていた。
今も、あの香水の匂いがふとした瞬間に蘇る。
夜のバー、カウンターの奥、電マの振動音、濡れた吐息──
すべてが“週末だけの現実”だった。だが、確かにそこに“沙月”はいた。
バーの灯りの奥に、彼女の残り香だけが、いまもまだ揺れている。