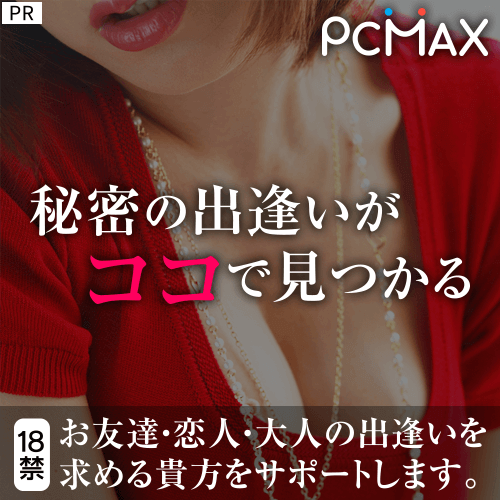-
相手:20代前半の爆乳女子高生(風の女性)
-
地域:大阪市内(駅は京都)
-
状況:彼氏持ちだが浮気癖があり、欲求不満気味
-
出会い:マッチングアプリ経由で知り合う(実質出会い系的な使い方)
-
プレイ:フェラ、ローター使用、足フェチ対応
-
性癖:自撮り好きで承認欲求が強く、軽度の露出嗜好も
-
性格:やや小悪魔系で甘え上手、内面に孤独感あり
「彼氏いるけど、セックス合わなくてさ。……エッチって、相性だと思うんだよね」
そんな一言から、全てが始まった。
彼女の名前は“あん”。年齢は20歳の女子大生──という設定だったが、初対面の写真はどう見ても「制服姿」。
そのマッチングアプリのプロフィールに記されていたのは、シンプルな一行だった。
《京都・大阪あたり。平日昼OKな人だけ》
ほぼそれだけだったが、アップされた写真の破壊力は強烈だった。
ピンクのカーディガンにネクタイ、プリーツスカート、そして圧倒的な胸。
明らかにEカップ以上、いやもしかするとFかGもあるかもしれない爆乳が、制服のシャツの前を引っ張っていた。
「これって、コスプレ? それとも……」と軽くメッセージを送った僕に、返事は思いのほか早かった。
《どっちがいい? リアルJKがよかったら、そういう設定でもいけるけど?(笑)》
まるで手慣れたキャバ嬢のような返しだったが、同時にどこか素のままの奔放さも漂っていた。
やり取りはテンポよく進み、お互いの趣味やNG、理想の時間帯なども確認し合った。
彼女は「エッチは好きだけど、軽く見られたくない」「甘やかされたいし、見られたい」と繰り返していた。
そして一言、こう送られてきた。
《会うなら……制服で行ったるわ。京都のホテル、予約しといて?》
会ったのは、京都駅の中央口。
改札前の人混みの中に、彼女はいた。
グレーのプリーツスカートに白いシャツ、黒のリボンにカーディガン。
足元はルーズソックスにローファー。制服コスとしては完璧すぎるほどだった。
そして何よりも……目を奪われたのは、やはり胸だった。
重力に逆らいながらシャツを押し上げるように主張する爆乳は、まさに“圧巻”だった。
「初対面やのに、そんなに見んの……? 変態やな」
そう言いながら、彼女はにやっと笑い、僕の腕に自然と絡んできた。
「でも、今日のあんは……ちょっとえっちかもしれんよ」
ホテルまでは徒歩5分ほど。
途中、彼女は何度もこちらを見上げてくる。
「ええ人そうやし、よかった。変な人も多いからな」
「ちなみに……あん、露出とか軽くなら好きやけど、ガチなのは無理やで?」
そんな風に、軽口を叩きながらも、自分の限界をしっかりと伝えてくる。
それが逆に「本物」だという信頼感を強めた。
ホテルのエレベーターでは、彼女が僕の指を絡め取り、手の甲に軽く唇を押し当ててきた。
「好きにしてええけど、優しくしてや?」
部屋に入ると、彼女はカバンを床に置き、ベッドに腰かけた。
「見せたげよっか?」
そう言いながら、彼女はカーディガンを脱ぎ、ボタンを一つずつ外していく。
Eカップどころではない。完全に爆乳級のGカップはありそうだった。
「ね? すごいやろ。たまにこの胸だけで会いたいって言われる。変な人やと、会って5分で揉まれるから」
「でも今日は……ええかも。ちゃんと、目で見てくれるし」
そう言いながら、彼女はローターを自分で取り出し、リモコンを渡してきた。
「ねえ……あんの足、好き? 触ってみて」
「ええよ。ローター、当てながら見ててな。ちょっと変態なこと、しよ?」
彼女の白い太ももは柔らかく、温かかった。
ルーズソックスを膝までずらし、ローターの先をパンティの上から押し当てると、彼女は目を閉じて喘ぎ声を漏らした。
「んっ……っ、あかん……もう、びくびくする……っ」
そのあとは、まさに“狂ったような午後”だった。
彼女は自らローターを操作し、制服姿のまま僕の太ももに跨ってきた。
その姿をスマホで撮ろうとすると、「ええよ、記念にして。顔は写さんといてな」と微笑んだ。
フェラの時は、最初は舌を這わせるように丁寧に、途中からは唾液を垂らしながら激しく。
視線はしっかりとこちらを見つめ、「あん、これ得意やねん」と笑う。
彼女の胸を揉むと、「そこ、ほんま……感じるねん」と声を漏らし、乳首を指で摘むと「イっちゃうかも……っ」と全身を震わせた。
潮吹きすら、未経験だったという彼女が、その日、初めてシーツを濡らした。
終わったあと、シャワーを浴びながら彼女が呟いた。
「……彼氏、全然触ってくれへんのに、浮気してるんちゃうかって疑ってくるねん」
「もう、愛されてるかどうかもわからん。でも、別れる勇気もない」
「だから、たまにこうやって“ちゃんと女として見てもらえる時間”が欲しいねん」
僕は何も言えず、ただ黙って彼女の背中にタオルを当てていた。
それから、僕らは3回の再会を重ねた。
2回目は梅田のホテル。
「足フェチやろ?今日はストッキング履いてきた」
そう言って、ベッドの上で脚だけを開いて、ストッキング越しに指を這わせる様子を自撮りしながらプレイした。
3回目は難波の個室レンタルルーム。
「撮影ええよ。音だけの動画も撮ろか?」
ローターを膣に当てながら、自分の喘ぎ声をスマホで録音し、再生して聞いて感じるという異常なほどの自己欲求の強さが、逆に愛おしくなった。
「誰かに、見られてたいねん。消費されてる方が、安心できる。変かな?」
そんなセリフに、僕は何も言えなかった。
それが彼女の“生き方”なのだと、ただ受け止めるしかなかった。
しかし──4度目の予定はキャンセルになった。
前夜、LINEが一通届いた。
《彼氏にバレたかも。携帯チェックされた。もう、会われへん。ごめんね。大好きやった》
短い文面だったが、そこにあんのすべてが詰まっていた。
いまでも、ときどき彼女のことを思い出す。
あの爆乳の柔らかさ、制服のしわ、汗ばんだ太ももの感触、
そして、弱くて孤独で、それでも誰かに見られたくて仕方がなかった彼女の目。
マッチングアプリを開いても、あの“あん”の名前はもう見つからない。
けれど僕の中には、今もあの日の午後の、あの淫らで切ない匂いが残っている。