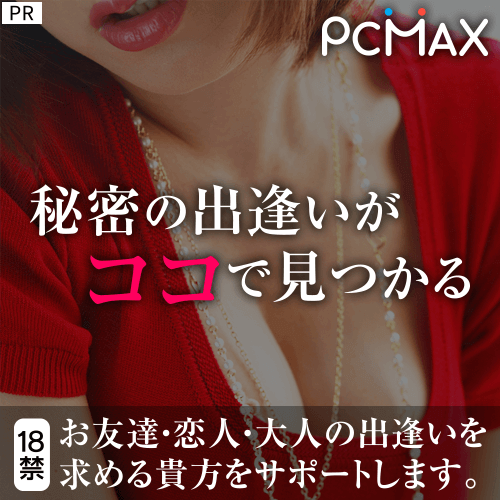大学時代からの癖のようなものだった。
夜、無意味にスマホを開いて、出会い系掲示板やマッチングアプリを徘徊する。
自分の欲望に名前をつけるなら、それは「中毒」だろう。
LINEにも連絡先はある。職場にも女性はいる。なのに、匿名の世界に惹かれるのは、きっと本当の自分がそこにしか存在しないからだ。
その夜も、関内の喫煙可能なネットカフェでPCMAXを眺めていた。
「19歳JD」「Aカップだけど感度◎」「不倫中」「中出しOK」「道具アリ」
あまりに直球なプロフィールだったが、写真に惹かれた。あどけない表情に、制服のような私服。どこか「ロリコン」を狙っている匂いがした。
即レスを送ると、5分もしないうちに返信があった。
《今日会えますか?バイブと電マ持ってきてます。ホテル代出してくれるなら大丈夫です》
少しも迷わずに、「関内駅南口、ドトール前で待ち合わせましょう」と送った。

彼女はそこにいた。
少し大きめのパーカーにミニスカート、足元は黒のニーハイソックス。
ぱっと見は高校生、いや、それより幼くも見えた。
でも、近づいて視線を交わした瞬間、彼女がただの少女ではないと理解した。
「……あなたが、メッセージの?」
声は小さく、視線は一度も僕を直視しなかった。
それでも、唇の端に浮かんだ笑みと、リュックの中から少し覗いたピンク色のバイブが、彼女の本気度を物語っていた。
そのまま近くのビジネスホテルへ入ると、彼女は部屋に入るなり靴を脱ぎ、ベッドに座り込んだ。
「今日、旦那が出張なの」
「……旦那?」
「うん、学生結婚なの。ほとんど会話ないし、もうレスで……一年以上」
そう言って、彼女は鞄から道具を取り出した。
バイブ、電マ、ディルド、スカイビーンズと、名前だけは知っていても、現物を初めて見る僕は言葉を失った。
「男の人ってさ、こういうの興奮するの?」
答えに詰まる僕を横目に、彼女はスカートをめくりあげ、下着を脱ぎ始めた。
Aカップらしい小ぶりな胸だったが、彼女の体には明らかに「性的な自信」があった。
一度開かれた扉は、もう閉じることはないという覚悟が、彼女の所作に表れていた。

彼女の名前は「みずき」。
神奈川県の大学に通う女子大生で、横浜市内の学生寮から週2、3で出会い系の男と会っている。
利用しているのは、主にPCMAX、ワクワクメール、ハピメなど。
彼女は、「LINE友達探しとか面倒で信用できない。だから掲示板の方が好き」と言った。
「セックスしたいとかエッチしたいって、男の人はすぐ書くじゃない?
でも私は、寂しいだけ。好きな人と、いっぱいイチャイチャして、オナニーの補助してもらいたいだけ」
その言葉に、僕は自分の期待がどんどん裏切られていくのを感じながらも、同時にどこか安心していた。
「前に三ノ宮で会った人はね、足フェチで。私のソックス舐めながらオナってた」
「変態って、すごい多いのよ。ローターでくすぐってきたり、フェラだけで済まそうとしたり……」
彼女の経験談は、まるで百戦錬磨のキャバ嬢のようだった。
それでも、どこか無垢で、脆くて、「抱きしめたくなる何か」があった。

数週間後、彼女に誘われて大阪の鶴橋へ行った。
「関西って、ほんとに援助交際掲示板が盛んなんだよ」
彼女は目を輝かせて言った。
「この前、京橋で3Pしたんだけど、一人はドSの主婦、もう一人は筆おろししてあげたいって会社員だったの。
二人とも60代近くて、体型はスレンダーと細身……でも、プレイはめっちゃ濃厚でさ」
僕が絶句していると、彼女は無邪気に笑った。
「やっぱ、セフレ掲示板って、年齢層広くて面白い。
この前なんか、ヤリモクアプリで知り合った人とカーセックスしたんだよ。
ドライブ中に突然『ここでやろう』って言われて。びっくりしたけど、なんか燃えちゃって」
その日の夜もホテルに入ると、彼女は「今日はアナルセックス試してみたい」と言い出した。
「怖いけど、信じてるから」
彼女のその言葉が、僕の中に妙な罪悪感と、奇妙な幸福感を生んだ。
出会いから3ヶ月が経ったころ。
彼女からの連絡頻度が徐々に減っていった。
秋葉原で最後に会ったとき、彼女はこう言った。
「私、恋しちゃったかも。でも、あなたじゃないの。ごめんね」
その一言で、すべてを理解した。
後日、彼女の掲示板アカウントは削除されていた。
彼女が誰と、どこで、何をしているのか。それを知る術は、もうどこにもなかった。

関内のホテルで交わした体温。
三ノ宮の路地裏で語られた性癖。
京橋で見せた少女のような微笑み。
鶴橋でつぶやいた「これが私のリアル」──
あの夜の全ては、僕の記憶と下半身に深く刻まれている。
彼女は、僕の「性」そのものを揺さぶり、同時に「孤独」という名の毒を与えて去っていった。
だから今夜もまた、僕はPCMAXの掲示板を開く。
そして、また誰かと出会うのだ。
それが人妻であれ、女子高生であれ、あるいはロリ系の処女であっても──
僕は、性欲と寂しさの境界で、ただ、「誰か」に会いたいだけなのだから。