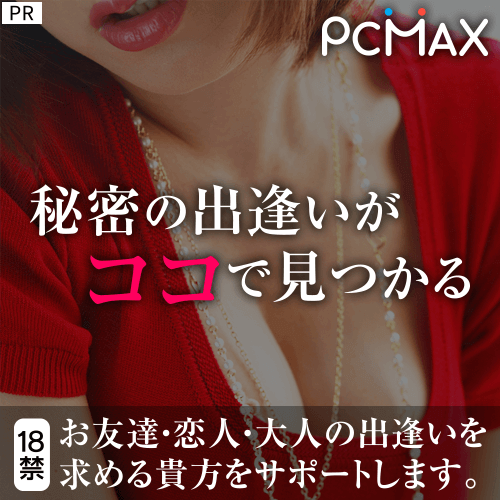スマートフォンの画面が、夜の部屋のなかで静かに光っていた。
デスクに積まれたままの書類、半分飲みかけの缶ビール。部屋の温度は適温だったけれど、胸の奥はどこか寒かった。
“誰かに触れたい”──そんな衝動は、季節の変わり目のせいにしておいた。
久しぶりに「PCMAX」にログインする。ときどきふとアクセスしてしまう、生活の“裏側”にあるようなアプリ。誰かと会うつもりがなくても、誰かの本音が見える気がして、癖のように開いてしまう。
その夜、目に止まったのは「なな」というユーザーだった。

◆ 「エッチしたいって、おかしいですか?」
プロフィールには、名前と年齢──「20歳 女子大生」──とだけ。
アイコンは、頬のラインだけが見える横顔の自撮り写真。けれど、その写真には何か“物語”が漂っていた。孤独と、それでも人に求められたいと願う気配のようなもの。
自己紹介文には、こう書かれていた。
「彼氏とはもう半年以上何もなくて。女の子として見られたいだけなのに、それもダメみたいで…エッチしたいって、変ですか?」
その文面に、僕は自然とメッセージを打っていた。
よくある釣りだとか、業者だとか、そんな可能性も頭をよぎったけれど、それ以上に“本音”が垣間見えた気がしたのだ。
◆ メッセージと沈黙のあいだに
最初のメッセージは、ただの挨拶だった。
「こんばんは。プロフィール、すごく素直で、なんか…惹かれました。」
ほどなくして返事が来た。
「こんばんは。こんな時間に見てくれる人、いるんですね。なんか、うれしいです。」
そこからの会話は驚くほどスムーズだった。ななは地方の進学校から都内の私立大に進学してきた文学部の学生で、部屋はワンルーム。高校時代からの彼氏とは大学に入ってすぐにすれ違いが始まり、会うたびに“義務的な関係”になっていったという。
「女の子って、抱きしめられたり、見つめられたり、触られたり、そういうことがないと、自分が“生きてる”感じがしなくなるんですよね。」
その言葉が印象的だった。性への欲望というより、“承認されたい”という孤独の延長線上にあるような、そんな響き。

◆ 「見て、ちゃんと私を見て」
会う約束は、すぐに決まった。
金曜の夜、池袋西口のカフェ。「緊張するから、少し早めに着いてます」とメッセージが届いたのは、待ち合わせの15分前だった。
実際に彼女を見たとき、最初の印象は「想像よりもずっと“普通”」だった。
白のブラウスにベージュのスカート、リュックを背負っていて、清楚で控えめな雰囲気。だけど、その肌の白さと、伏し目がちな横顔に色気があった。
「すみません、なんか…こういうの、はじめてで。」
言葉の端々から、不安と期待がにじんでいた。
カフェでは、大学での授業の話、ゼミのテーマ、小説の好み、そして「最近よく泣いてしまう」ことなどを語ってくれた。
“女子大生”という肩書きの奥に、誰かに見つめてほしい、価値を感じてほしいという、あまりにも人間らしい欲求があった。
「今日だけでいいんです。ちゃんと、私を“女の子”として見てくれるなら、それだけで。」
その目は真っ直ぐで、嘘がなかった。
◆ 指先から伝わる温度と湿度
ホテルの部屋に入っても、彼女はしばらく黙っていた。
僕はあえて何も言わず、飲み物だけ用意してベッドに座った。
その静けさの中で、彼女はふいにこう言った。
「ねえ、目、閉じてて。」
その声に従って目を閉じると、数秒後、柔らかい唇が僕の唇に重なった。
彼女から、そっとキスをしてきたのだ。
それは震えるような、でも確かな意志のあるキスだった。
その後、彼女は服を脱ぎはじめた。
下着姿になると、彼女は静かにこちらに背を向けて「…どう?変じゃない?」と聞いた。
「すごく、綺麗だよ。」
Aカップの胸、細い腰、なだらかな背中のライン──それは華奢で、それでいて確かな色気を持っていた。
彼女は恥ずかしそうにベッドに横になり、僕の手を引いた。
「やさしくしてね。乱暴じゃなくて、ちゃんと触れてほしい。」
その声は、どこまでも真剣だった。

◆ ゆっくりと“女”になっていく
クンニをすると、彼女の太ももがわずかに震えた。
「そんな…恥ずかしい」と言いながらも、拒むことなく受け入れてくれた。
その後、彼女はフェラをしてくれた。ぎこちない動きだったが、その不器用さがむしろリアルで、“与えたい”という気持ちが伝わってきた。
セックスのとき、彼女は少しだけ涙を流した。
「なんか、うれしくて、泣いちゃいそう…」
痛みと快感の狭間で揺れながら、少しずつ“女”としての感覚を思い出していくような表情。僕は何度もキスをしながら、彼女の名前を呼んだ。
最後は中で果てた。
「中でいいよ。今日は、全部ほしい。」
それが、彼女の本音だったのかもしれない。

◆ 余韻と、朝焼けと、見えない未来
終わった後、彼女はシャワーを浴びてから、ベッドで僕の隣に横になった。
濡れた髪のまま、僕の腕に頭を預けて、ぽつりとこう言った。
「また、会いたいな。…でも、期待しないでね。」
それが、彼女のなりの“自衛”だったのかもしれない。
関係を深くすることへの恐れ。手放すことへの覚悟。
タクシーに乗り込む彼女を見送ったあと、スマホの画面には「ありがとうね。またね」という短いメッセージが残っていた。
それが、最後だった。
◆ 終章──女子大生という仮面と、本当の欲望
“女子大生”という言葉には、幻想がつきまとう。
若さ、未熟さ、清純さ。けれど、出会い系で出会った彼女は、そのどれにもおさまらない“ひとりの人間”だった。
PCMAXでの出会いは、偶然のようで必然だったのかもしれない。
ななが欲しかったのは、身体だけじゃない。
きっと、“誰かの目に映る自分”だったのだ。
そんな彼女の心に、ほんの少しでも触れることができたなら。
僕はその夜を、ずっと忘れない。